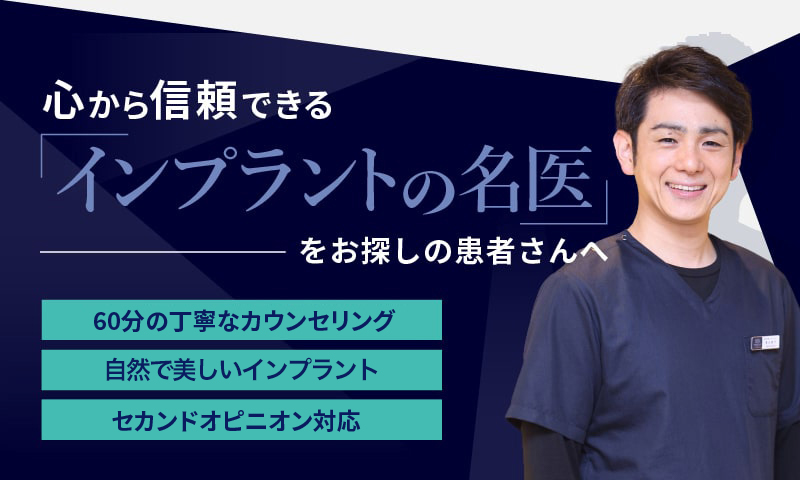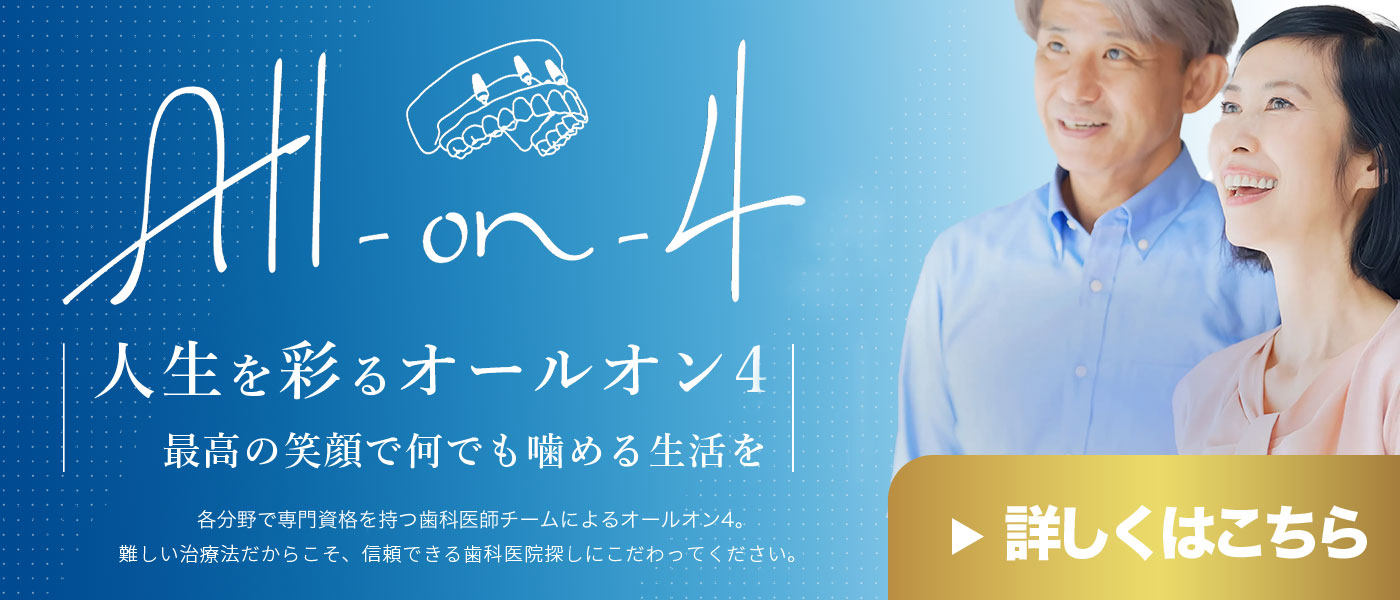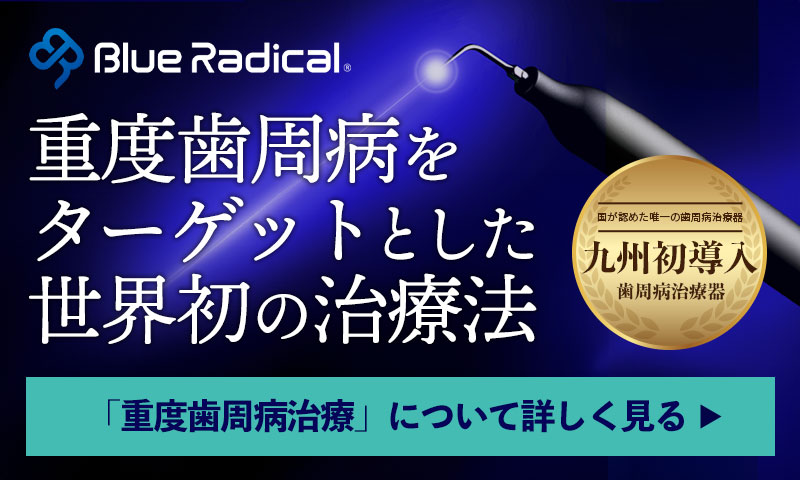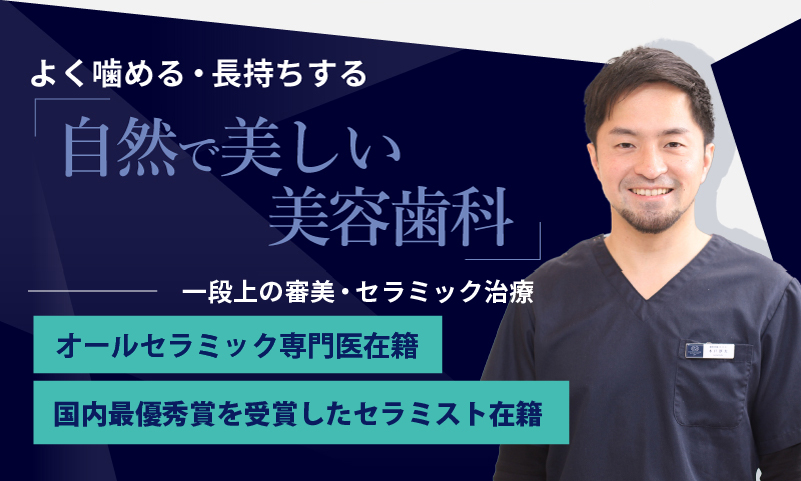インプラントで骨を作る
「骨造成」とは?
メリットやデメリット、
治療の流れについて解説
インプラント治療を行う際、顎の骨の量が不足しているとそのままではインプラントを埋め込むことができないことがあります。
そこで必要になるのが骨造成です。
骨造成とは、不足している顎の骨を補い、インプラントがしっかり安定する土台を作るための治療法です。
ここでは、骨造成が必要となる理由、具体的な方法、メリットやデメリット、治療の流れについて詳しく解説していきます。
骨造成とは?

骨の量・厚みを補う治療
骨造成とは、インプラント治療を行う際に必要な骨の量や厚みが不足している場合に行われる治療で、骨移植や人工的な再生材料を用いて、失われた骨を補い増やすことを目的としています。
歯を失った部分の骨は、噛む刺激を受けなくなることで徐々に吸収され薄くなり、さらに歯周病の進行や外傷、長期間の入れ歯使用などによっても減少してしまいます。
そのため、骨が不足した状態で無理にインプラントを埋め込むと、固定が不十分でインプラントが脱落するリスクが高くなりますが、骨造成を行うことで十分な骨量を確保することができ、インプラントを長期的かつ安定的に機能させる治療が可能となります。
骨造成が
必要になるケース

歯周病で骨が溶けている場合
歯周病は歯を支える骨を徐々に破壊する病気です。重度に進行すると歯が抜け落ちるだけでなく、顎骨そのものが大きく吸収されてしまいます。
このような場合、そのままではインプラントを支える骨が足りず、骨造成によって失われた骨を補う必要があります。
特に全顎的に歯周病が進行している人は、広範囲の骨造成が必要となることもあります。
抜歯から時間が経っている場合
歯を失った直後は骨の量がある程度保たれていますが、数ヵ月〜数年経過すると骨は急速に痩せていきます。
特に抜歯から数年以上経過した部位では、顎骨が平坦化してしまい、インプラントを固定するスペースが残っていないことも珍しくありません。
こうしたケースでは骨造成を行い、インプラントが安定する十分な骨の高さや幅を再生することが必要となります。
上顎洞に近い部位のインプラント
上顎奥歯の部位は、鼻の横にある上顎洞という空洞に接しているため、骨の厚みが非常に薄いことが多いです。
この場合、そのままインプラントを埋め込むと上顎洞を突き破ってしまう危険性があります。そこで行われるのがソケットリフトやサイナスリフトといった骨造成法です。
これにより、安全に骨の高さを確保し、長期安定性を得ることが可能となります。
外傷や腫瘍などで
骨が失われた場合
事故やスポーツ外傷で顎骨が損傷したり、腫瘍切除手術などで骨を失った場合にも骨造成が必要です。
失われた範囲が広い場合は、大規模な骨移植や特殊な再生治療が必要になることもあります。
骨造成の種類と方法

GBR法
GBR法は比較的小規模な骨欠損に適した方法です。人工骨や自家骨を欠損部分に入れ、メンブレンと呼ばれる特殊な膜で覆うことで、骨が再生しやすい環境をつくります。
数ヵ月後には新しい骨が形成され、インプラントを支えられる状態になります。
治療の侵襲が比較的少ないため、多くの歯科医院で採用されています。
ソケットリフト
ソケットリフトは、上顎洞の底部をインプラントを埋入するための穴から押し上げて人工骨を入れる方法です。
骨の高さがあと数ミリ足りないといった軽度の不足に適しています。
外科的負担が小さく、治療後の腫れや痛みも比較的軽いことが多いため、上顎奥歯における骨造成の第一選択となることもあります。
サイナスリフト
サイナスリフトは、骨の不足が大きい場合に行われる方法です。
歯肉を切開し、歯槽骨に穴をあけ、横から上顎洞にアプローチして粘膜を持ち上げ、その空間に人工骨を充填します。
骨の高さを大きく増やせる反面、術式が難しく手術時間も長めになります。
大規模な骨造成が必要なケースでは非常に有効です。
ブロック骨移植
患者様ご自身の顎骨や腰の骨からブロック状に骨を採取し、必要な部位に移植する方法です。
人工骨では対応できない大きな骨欠損に用いられることが多く、確実に骨量を増やすことができます。
ただし骨を採取する部分への外科的負担が大きく、手術後に腫れや痛みが出やすいのがデメリットです。
人工骨移植と自家骨の併用
近年では人工骨と自家骨を併用することで、それぞれの長所を生かす治療も行われています。
人工骨は感染リスクが少なく手術が簡便、自家骨は生着率が高く骨形成が良好という特徴があり、これらを組み合わせることで安全性と確実性を両立させることができます。
骨造成のメリット

インプラント治療の
適応範囲が広がる
骨造成を行うことで、これまで骨量不足のためインプラントが難しいとされていた方でも治療が可能になります。
特に高齢の方や歯周病で骨が痩せてしまった方にとっては、再びインプラントという選択肢を得られることは大きな利点です。
長期安定性の向上
十分な骨にしっかりと支えられたインプラントは、噛む力を均等に分散できるため長期的に安定します。
土台がしっかりしていれば、人工歯の交換やメンテナンスを行いながら、10年、20年と使い続けることが可能になります。
審美性の改善
骨が痩せてしまうと歯肉の形も不自然になり、人工歯を入れても境目が目立ってしまうことがあります。
骨造成を行うことで歯肉ラインが整い、きれいな見た目になります。
特に前歯のインプラントでは、この審美性の改善は大きなメリットです。
将来的な治療の選択肢を残せる
骨をしっかり作っておけば、将来的にインプラントが外れたり修復が必要になった場合でも、再治療の選択肢を残すことができます。
骨がない状態のままでは後の対応が難しくなるため、骨造成を行っておくことは未来への備えともいえます。
骨造成のデメリット

治療期間が延びる
骨が安定するまでには数ヵ月の治癒期間が必要です。
そのため、インプラント治療全体の流れが長期化し、治療完了までの時間的な負担が増えます。
追加の費用がかかる
骨造成はインプラント本体の治療費に加算されるため、数万円〜数十万円の追加費用が発生します。
骨の量や治療方法によって費用は変動し、思った以上に高額になるケースもあります。
手術による負担
骨造成は小規模な処置から本格的な骨移植まで幅広くありますが、外科手術である以上、腫れや痛み、出血といった術後の負担が避けられません。
特にブロック骨移植などでは骨を採取する部分にも影響が及び、患者様の身体的な負担は大きくなります。
成功率に個人差がある
全員が同じように骨が再生するわけではありません。
喫煙習慣や糖尿病、免疫力の低下などがあると骨の治癒が不十分になり、期待通りの結果が得られないこともあります。
そのため、生活習慣の改善や全身管理も並行して行うことが重要です。
骨造成の治療の流れ

1.カウンセリング、診査
まずはカウンセリングで患者様の希望や不安を確認し、CT撮影や模型を用いて顎の骨量や厚みを検査します。
インプラントを埋入するために骨造成が本当に必要かどうかを見極め、治療計画を立てます。
2.手術
骨が不足している部分に人工骨や自家骨を補い、必要に応じてメンブレンで覆い、骨が再生する環境を整えます。 小規模な処置で済む場合もあれば、全身麻酔下で行う大掛かりな骨移植になる場合もあります。
3.治癒期間
骨が新しく形成され、安定するまで数ヵ月の期間が必要です。
患者様によっては6ヵ月〜1年ほどかかることもあります。
この間は定期的なチェックを受け、感染予防や生活習慣の管理が欠かせません。
4.インプラント埋入
骨造成で十分な骨量が確保できたら、いよいよインプラント埋入手術を行います。
症例によっては骨造成とインプラント埋入を同時に行うこともありますが、成功率や安定性を重視して段階的に行うことも多いです。
5.人工歯の装着
インプラントと骨がしっかり結合したことを確認した後、人工歯(を装着します。 ここで噛み合わせや見た目を調整し、周囲の歯となじむような仕上がりになるようにします。
骨造成を受ける際の
注意点

術後の腫れや痛み
手術後は数日間腫れや痛みが出ることがありますが、処方された薬を服用すれば多くは数日で落ち着きます。
生活習慣の改善
喫煙や過度な飲酒は骨の治癒を妨げるため、術前から控えることが重要です。
メンテナンス
骨造成後は感染予防が不可欠です。毎日のセルフケアに加え、歯科医院での定期的なクリーニングを続ける必要があります。
全身疾患との関係
糖尿病や骨粗しょう症などの持病がある場合は、主治医と連携して全身管理を行うことが求められます。
インプラントを入れる
下準備、骨造成

骨造成で広がる
インプラント治療の可能性
骨造成は、インプラント治療を希望しているにもかかわらず骨が足りないと診断された方にとって、治療の可能性を広げる大切な技術です。
治療期間や費用の負担は増えますが、長期的な安定性や自然な見た目を得られる大きなメリットがあります。
インプラント治療を検討する際には、骨造成が必要かどうかをまず確認し、経験豊富な歯科医師のもとで適切な治療計画を立てることが大切です。

 初診限定|ネット予約はこちら
初診限定|ネット予約はこちら  相談はこちら
相談はこちら