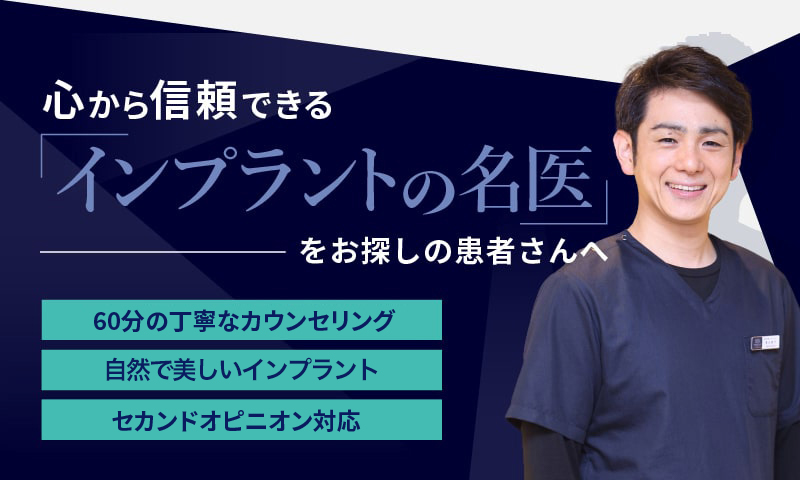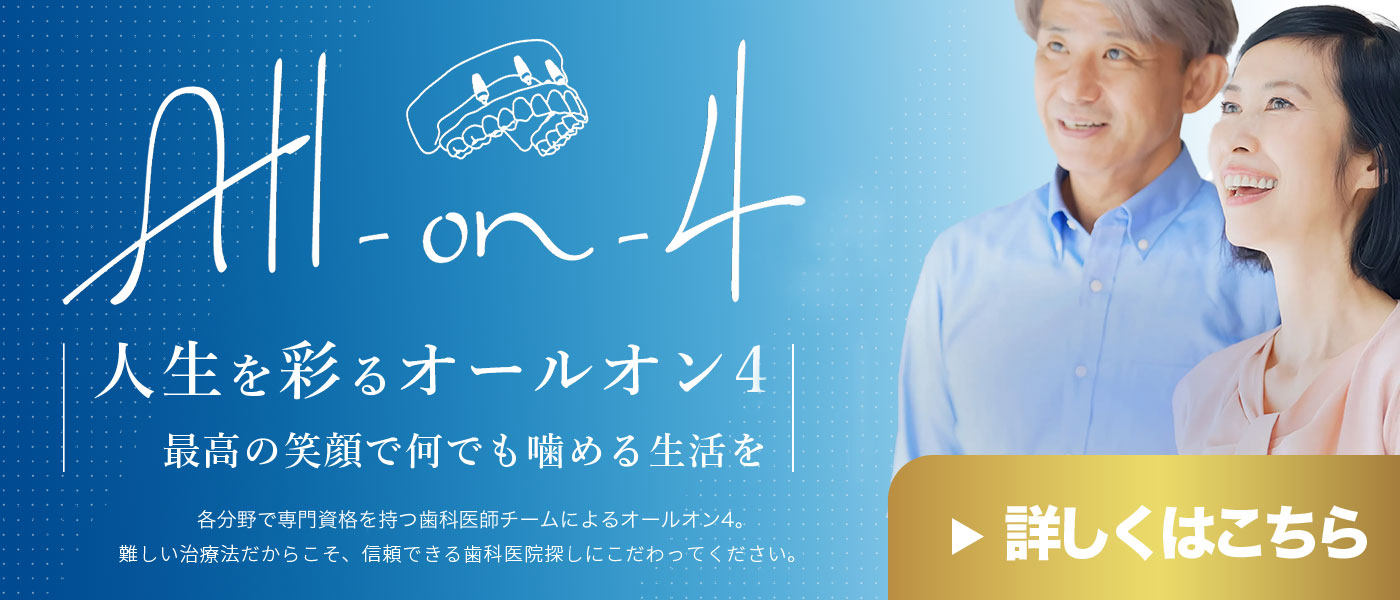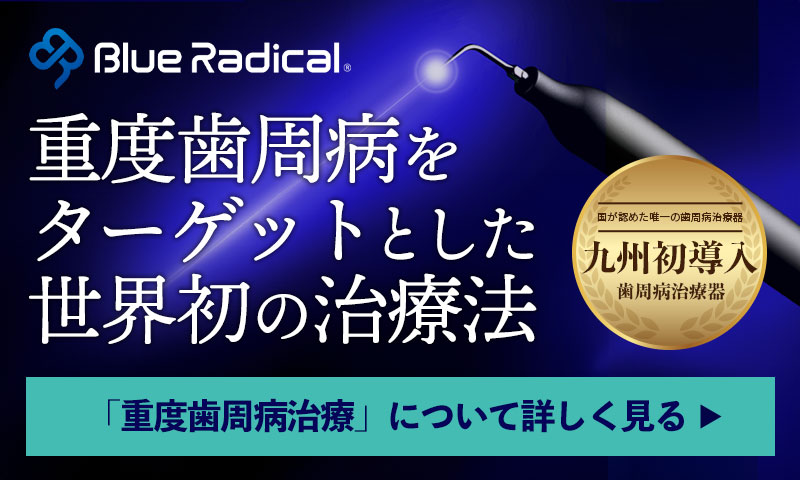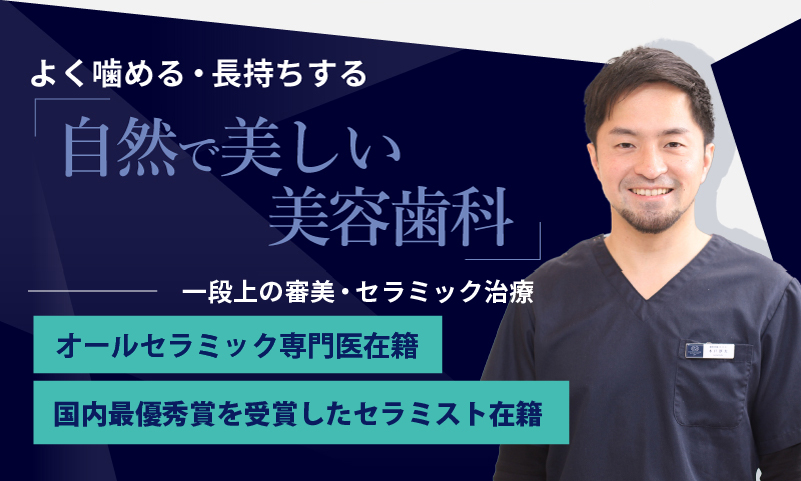インプラント周囲炎の
原因とは?
インプラントを
長持ちさせるための
ポイントを解説
インプラントは埋入して終わりではありません。
手入れやメンテナンスを怠るとインプラント周囲炎という病気を起こし、最悪の場合インプラントを失うリスクもあります。
ここでは、インプラント周囲炎の原因や症状、治療法、そして長持ちさせるためのセルフケアとメンテナンスのポイントについて詳しく解説します。
インプラント周囲炎とは
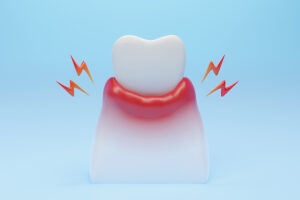
歯周病に似た病気
インプラント周囲炎とは、インプラントを支える歯肉や骨に炎症が起こる病気です。
天然歯の歯周病に似ていますが、インプラントには歯根膜がないため炎症が進行しやすく、骨吸収が急速に進むことがあります。
初期は自覚症状が少なく、気づかないうちに進行するのが特徴です。
痛みが出る頃には骨が大きく失われていることも多く、早期に異変に気づくことが何よりも重要です。
インプラント周囲炎の原因

プラークコントロール不足
インプラント周囲炎の最大の原因は、プラークコントロール不足です。
インプラントは天然歯と比べると表面が滑らかで一見汚れがつきにくいように見えますが、歯肉との境目にはわずかな段差があり、そこに細菌が集まりやすくなります。
天然歯には歯根膜というクッションが存在し、防御機能や血液供給がある程度働きますが、インプラントにはそれがないため、一度細菌が付着すると炎症が急速に広がるのです。
磨き残しが続けば、プラークは数日で硬い歯石に変わり、通常の歯ブラシでは取り除けなくなります。
結果として細菌が住みつきやすい環境となり、慢性的な炎症の引き金になります。
歯周病の既往
インプラント周囲炎と歯周病は非常に関連性が強い病気です。
過去に歯周病を経験した人は、そうでない人に比べてインプラント周囲炎を発症するリスクが高いとされています。
これは、口腔内に歯周病菌が残っていたり、炎症に対する抵抗力が弱まっていたりすることが背景にあります。
そのためインプラント治療を始める前に、歯周病の治療と管理を徹底することが必要です。
また、歯周病の再発を防ぐために、定期的なメンテナンスとセルフケアの習慣化も強く求められます。
生活習慣の影響
生活習慣もインプラント周囲炎の大きな原因です。
特に喫煙は、インプラントの成功率を下げる代表的なリスク要因です。
タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させる作用があり、歯肉への血流が悪くなります。
その結果、酸素や栄養が十分に届かず、免疫力が低下し、炎症が治りにくくなります。
また、骨とインプラントが結合するオッセオインテグレーションを妨げるため、喫煙者は非喫煙者に比べて治療後のトラブルが多いことが分かっています。
さらに、糖尿病や高血圧などの全身疾患も炎症を悪化させやすい要因です。
血糖コントロールが不十分な糖尿病患者様は、免疫細胞の働きが低下して傷の治りが遅くなり、感染リスクが高まります。
その他にも、過度な飲酒、睡眠不足、栄養バランスの偏りなども免疫力を下げ、インプラント周囲炎の発症につながります。
噛み合わせや力のかかりすぎ
見落とされがちですが、噛み合わせの不調和や強い食いしばり、歯ぎしりもインプラント周囲炎の原因になります。
インプラントは天然歯のような歯根膜がないため、力が直接骨に伝わりやすく、その結果、骨が徐々に吸収され炎症を起こしやすくなります。
特に夜間の歯ぎしりは無意識に強い力をかけてしまうため、ナイトガードの装着を指導されることもあります。
インプラント周囲炎の
治療法

クリーニング
軽度であれば、歯科医院でプラークや歯石の除去をすることで改善するケースもあります。
場合によってはエアフローも用いられます。
抗菌療法
細菌の活動を抑えるために、抗菌薬を服用したり、歯周ポケット内に抗菌ジェルや薬剤を注入することがあります。
局所的な洗浄により炎症を一時的に鎮めることができ、クリーニングと併用することで効果が高くなります。
ただし、薬だけでは再発を防げないため、日常のセルフケアとセットで行うことが基本です。
外科的処置
炎症が深部に及び、骨吸収が進んでいる場合には外科的治療が必要となります。
歯肉を切開して感染した組織を除去し、インプラントの表面を洗浄します。
必要に応じて人工骨やメンブレンを用いた骨再生療法(GBR)を行い、失われた骨を補うこともあります。
歯肉移植を行って歯肉の厚みを回復させるケースもあり、インプラントを守るために複数の方法が組み合わされることもあります。
インプラント撤去
重度の場合はインプラントを保存できず、撤去を選択するケースもあります。
撤去後は感染部分の治療を優先し、骨や歯肉の状態が整ってから再度インプラントを検討する流れです。
すぐに再埋入できることもありますが、炎症の程度によっては数ヵ月〜1年以上待つこともあります。
インプラントを
長持ちさせるための
セルフケア

正しい歯磨き
インプラントの周囲は天然歯よりもプラークがたまりやすく、歯ブラシが届きにくい部位も多いのが特徴です。
歯ブラシは硬すぎない毛先の細いタイプを選び、歯と歯肉の境目を小刻みに動かして磨くことが大切です。
特にインプラントとアバットメントのつなぎ目は汚れが残りやすいため、タフトブラシを併用すると効果的です。
また、電動歯ブラシを正しく使うと、短時間で効率的に清掃できます。
歯間清掃
インプラントと隣接歯の間も、プラークが残りやすい代表的な部位です。
歯間ブラシはサイズが合っていないと歯ぐきを傷つける可能性があるため、歯科医院でサイズを確認すると安心です。
フロスは狭い部分に有効で、インプラント周囲に巻き付けて上下に動かすように使います。
洗口液を取り入れる
抗菌成分入りの洗口液は、歯ブラシやフロスだけでは届かない部分に作用し、細菌の繁殖を抑えます。
ただし使えば磨かなくてもよいというものではなく、あくまで補助的な役割です。
アルコール入りのものは刺激が強いため、歯肉が弱い方や長期使用には向かない場合があります。
使用方法や頻度は、歯科医師や歯科衛生士に相談して自分に合ったものを選ぶと良いでしょう。
インプラントを守るために
気をつけたい生活習慣

喫煙習慣の改善
喫煙はインプラント治療の成功率を下げる最大の要因の一つです。
タバコの煙に含まれる有害物質が歯肉の血流を阻害し、炎症が治まりにくくなります。
また、免疫力の低下で細菌感染を助長し、インプラント周囲炎のリスクを高めます。
禁煙が難しい場合は、まずは本数を減らすことからでも始め、歯科医院や医科の禁煙外来と連携するのも有効です。
食生活に注意
柔らかい食事ばかりに偏ると咀嚼力が低下し、顎や筋肉の発達が不十分になります。
一方で、極端に硬い食品ばかりを噛むこともインプラントに負担になります。
肉や魚、野菜、穀物をバランスよく摂取し、適度な硬さの食品を噛む習慣を持つことが大切です。
全身疾患の管理
糖尿病や骨粗しょう症、高血圧などの全身疾患は、インプラントの予後に直接影響します。
血糖コントロールが不十分な場合、免疫機能が低下し感染が広がりやすくなりますし、骨粗しょう症では骨の質が低下してインプラントの安定性に影響が出ることもあります。
持病がある方は必ず主治医と情報を共有し、歯科と医科の両方で全身管理を徹底することが、インプラントを長持ちさせる秘訣です。
インプラントの寿命は
どれくらい?

インプラントを
長く使うために大切なこと
インプラントの寿命は一概に決まっているわけではなく、日々のセルフケアや生活習慣、定期的なメンテナンスによって大きく左右されます。
一般的には10年以上の長期使用が可能で、条件が整えば20年近く安定して使えるケースもあります。
ただし、人工歯の部分は摩耗や劣化が避けられず、数年から10年程度で調整や交換が必要になることがあります。
下顎は骨が硬く安定しやすい一方、上顎は骨が柔らかく副鼻腔の影響も受けやすいため、同じインプラントでも部位によって寿命が異なります。
さらに喫煙や糖尿病、歯ぎしりといった要因は大きなリスクであり、インプラント周囲炎の発症や骨吸収を早める可能性があります。
定期検診を3ヵ月ごとに受け、噛み合わせや歯肉の状態を確認し、歯間ブラシやタフトブラシでの清掃を習慣化することで寿命は大きく延ばせます。
インプラント周囲炎に気を付け、長くインプラントを使えるようにしましょう。
インプラント周囲炎を
防ぐのが寿命を延ばす
ポイント

インプラントを
長持ちさせるために
大切なケアと習慣
インプラント周囲炎は、インプラントにとって最大のリスクともいえる病気です。
原因はプラークの蓄積や生活習慣の乱れ、既往歴などさまざまですが、正しいセルフケアと定期的なメンテナンスで多くは予防できます。
治療後の快適な生活を長く続けるためには、患者様ご自身の意識と歯科医院との二人三脚が欠かせません。
インプラントを長持ちさせたい方は、ケアを見直し、定期的な検診を欠かさず受けることをおすすめします。

 初診限定|ネット予約はこちら
初診限定|ネット予約はこちら  相談はこちら
相談はこちら